「また今日も休みかよ…」
朝の出勤時間8時30分。いつものデスクが空いているのを見て、思わずため息が漏れる。昨日の夕方「明日は必ず来ます」って言ってたはずなのに。またLINEで「体調不良でお休みします」の短文メッセージ。結局、その人の仕事は誰がやると思ってるんだろう。
正直、もう信用できない。
週に2〜3回は必ず休む同僚。月曜日と金曜日の欠勤率は異常に高い。そして必ず連休の前後、給料日の翌日、繁忙期のど真ん中。理由を聞けば毎回「体調不良」「家庭の事情」「突然の体調不良」のオンパレード。でも、SNSを見れば元気そうな投稿が午後にアップされていて…。「体調不良で休んだのに、友達とランチ?」そんな疑問がどんどん膨らんでいく。
「私だって休みたい日はある。家族との時間も欲しい。でも、責任感があるから体調が悪くても這ってでも出社してるのに」
「なんで私だけがいつも残業して、その人のフォローをしなければいけないの?」
「上司はなぜ何も言わない?見て見ぬふりをしているの?」
こんな不満、あなたも抱えていませんか?
真面目に働いている人ほど、よく休む人に対して強い不信感を抱いてしまうもの。それは決しておかしなことではありません。むしろ、責任感のある人として当然の感情です。毎日きちんと出勤して、チームのために頑張っているあなたの気持ちは、本当によく分かります。
毎朝「今日は来るかな?」と不安になり、午前中の時間を欠勤者の業務調整に費やし、夕方には「また明日もこの人の分の仕事をしなければ」という憂鬱感に襲われる。こんな日々を送っていると、仕事へのモチベーションも下がってしまうのは当然です。
でも同時に、冷静になった時、こんな疑問も浮かんでくるはずです。
「本当に体調が悪いのかもしれない」
「家庭で大変な事情があるのかもしれない」
「でも、それなら何か対策はないの?」
「このまま我慢し続けるしかないの?」
この記事では、「よく休む人は信用できない」という素直で正当な感情に真摯に向き合いながら、なぜそう感じるのか、どう対処すべきなのか、そして最終的にはどうすればお互いが働きやすい環境を作れるのかを一緒に考えていきます。
感情論だけでなく、実践的な解決策も含めて、あなたの気持ちに寄り添いながら、建設的な道筋を見つけていきましょう。
なぜ「よく休む人は信用出来ない」と感じてしまうのか
まず最初に、あなたが感じている「信用できない」という気持ちは、決して間違っていません。多くの働く人が同じような感情を抱いています。厚生労働省の調査によると、職場での人間関係トラブルの約30%が「勤務態度の問題」に関連しており、その中でも「頻繁な欠勤」は最もストレスの高い要因の一つとされています。
仕事のしわ寄せで感じる理不尽な思い
よく休む人がいる職場で最も辛いのは、その人の仕事が自動的に自分に降りかかってくることです。これは単なる「お手伝い」の域を超えて、構造的な問題となっています。
朝9時、出社してすぐに上司から「○○さん急に休みなので、この案件お願いします」と言われる。自分の今日の予定はすでにぎっしり詰まっているのに、突然追加の業務が降ってくる。午前中は急遽その対応に追われ、本来の自分の仕事は後回し。結果として残業時間が増える一方で、特別な手当てや評価はもらえない。
そして休んだ人は翌日、何事もなかったかのようにケロッとして出社。「昨日はお疲れ様でした」「ありがとうございました」の一言すらない。それどころか「昨日何かありました?」と他人事のような態度。そしてまた数日後、同じパターンの繰り返し。
実際の声
「週3回は休む同僚のせいで、私の残業時間が月40時間も増えました。でも給料は変わらないし、評価も上がらない。本当に理不尽です。家族との時間も削られて、もう限界です」(30代・女性・事務職)
「私が有給を取ろうとすると『忙しいから難しい』と言われるのに、あの人はいつでも自由に休める。同じ会社の同じ部署なのに、なぜこんな差があるのか理解できません」(20代・男性・営業)
この感情は至極正常な反応です。努力が報われない虚しさ、負担の偏りによる怒り、慢性的な疲労の蓄積、仕事へのモチベーションの低下を感じるのは、あなたが責任感を持って真面目に働いている証拠です。こうした気持ちを抱くのは、決してあなたの心が狭いからではありません。
責任感のギャップが生むストレス
真面目に働く人は深く根ざした価値観を持っています。「仕事は責任を持つべき」「チームに迷惑をかけてはいけない」「約束は必ず守る」「体調が悪くても這ってでも出社する」。これらは幼少期からの教育や社会経験を通じて培われた、職業倫理の根幹です。
一方で、よく休む人の行動パターンは真逆に見えます。些細な理由で気軽に休み、周りへの配慮や事前相談が不足し、「明日は来ます」と約束しても平気で破り、急な欠勤を何度も繰り返します。
この価値観の根本的な違いが、様々な負の感情を生み出します:
- 怒りと不信感:「なぜあの人だけ許されるのか」
- 失望と諦め:「真面目にやるのがバカらしい」
- 裏切られた感:「チームワークなんて幻想だった」
- 深刻な不公平感:「努力が報われない世界」
責任感の違いは具体的な業務への悪影響も引き起こします。仕事の品質低下(急な代理対応による準備不足)、顧客対応の遅れ(担当者不在による連絡取れず)、チーム目標の未達成(人員不足による作業遅延)、職場の雰囲気の悪化(不満とストレスの蔓延)といった、経営にも関わる深刻な問題へと発展していきます。
誰もが抱える「不公平感」の正体
人間は本能的に「公平性」を求める生き物です。これは進化心理学の研究でも証明されており、不公平な状況に対する脳の反応は、物理的な痛みと同じ部位を活性化させることが分かっています。
具体的な不公平感の例を見てみましょう:
勤務態度の格差
- 自分:体調悪くても解熱剤飲んで出社 → 相手:微熱程度で即欠勤
- 自分:家族の用事があっても仕事優先 → 相手:「子供の学校行事」で平日休み
- 自分:有給申請は1か月前から → 相手:当日の朝「急に休みます」
労働負荷の格差
- 自分:毎日残業、休日出勤も → 相手:定時退社、有給フル消化
- 自分:難しい案件もすべて引き受ける → 相手:「できません」「分かりません」
- 自分:他部署からの依頼も断れない → 相手:「忙しいので無理です」
評価・待遇の格差
- 自分:毎月目標達成しても評価B → 相手:目標未達でも同じ評価B
- 自分:昇進試験に何度も落選 → 相手:なぜか昇進
- 自分:ボーナス査定「もう少し頑張れば」 → 相手:同額支給
このような状況で不公平感を感じると、生理学的にも深刻な影響が現れます。ストレスホルモン(コルチゾール)の慢性的な増加、モチベーション物質(ドーパミン)の分泌低下、仕事への意欲と集中力の著しい減退、同僚や組織への深刻な人間不信、さらには不眠・頭痛・胃痛といった心身の不調まで引き起こします。
「よく休む人を信用できない」と感じるのは、決して心が狭いわけではありません。公平性を重視し、責任感を持って真面目に働いているからこそ感じる、極めて正当で健全な感情なのです。
よく休む人が信用出来ないと感じる現実的な理由
感情論だけでなく、実際の業務への影響を見てみると、信用できないと感じる理由がより明確になります。
突然の欠勤で現場が混乱する実態
ある月曜日の朝の惨状を、時系列で追ってみましょう。これは多くの職場で実際に起きている現実です。
8:30 「○○さんから体調不良で休みの連絡」が入る。その日は重要なクライアントプレゼンの日。
8:35 上司がパニック状態で「今日の会議どうする!?資料は?担当者がいない!」
8:40 急遽、代理を探し始める。「誰かあの案件知ってる人いる?」「パスワード分かる人?」
8:50 資料の在り処が分からず右往左往。ファイルサーバーのどこ?メールで送った?紙で印刷した?
9:00 会議開始も準備不足でグダグダ。「すみません、担当者が急遽休みで・・・」
9:30 クライアントから苦情の電話。「こんなプレゼンで契約できるわけないでしょう」
10:00 他のメンバーで業務を急遽分担。本来の予定はすべて後回し。
12:00 明日締切の他の案件も、皆で残業で対応することが決定。
18:00 結局全員が残業確定。最終電車で帰るメンバーも。
20:00 家族への「今日も遅くなる」の連絡が、皆のスマホから一斉に送信される。
現場の生の声
「月曜の朝8時30分、『今日休みます』のLINE一本。その日は半年準備した大事なプレゼンだったのに。結局、徹夜で作った資料も無駄になり、500万円の契約も流れました。会社にとっても、チームにとっても大きな損失です」(30代・男性・営業)
「システムメンテナンスの日に、エンジニアが突然休み。作業手順を知ってるのはその人だけ。サーバーダウンが6時間続き、顧客からのクレームが止まらなかった」(20代・男性・IT)
締切や納期への影響という深刻な問題
ビジネスの世界は時間との勝負です。一人の欠勤が、どれほど大きな波紋を広げるのか、具体的な数字で見てみましょう。
顧客対応への影響
- 問い合わせ回答の遅延:平均1日 → 最大3日
- クレーム発生率:通常時の3倍、顧客満足度の低下
- リピート受注率:15%減(信頼関係の悪化による)
- 紹介率の低下:新規顧客獲得の機会損失
プロジェクト遅延のコスト
- 人件費の増加:残業代、休日出勤手当
- 外部业託費用:急遵対応のため割高に
- 設備・オフィスコスト:プロジェクト期間延長
- 機会損失:競合他社に先を越される
実際の損害事例
「デザイナーが締切前日に突然休んで、クライアントへのプレゼンが延期。結局、競合他社に決定。違約金100万円に加え、年隓4000万円の取引を失いました」(40代・男性・ディレクター)
「結婚式場のコーディネーターが当日の朝に欠勤。200組のカップルとゲストが待つ中、急遵代理で対応。トラブルが続出し、損害賺償請求されました」(30代・女性・イベント業)
「医療系システムのメンテナンス日にエンジニアが休み。病院のシステムが6時間ダウン。患者情報の参照できず、一部の手術が延期に。システム復旧に200万円、病院からの损害購償で3000万円でした」(40代・SE・システム会社)
これらはすべて「たった一人の欠勤」が引き起こした、実際の损害事例です。
チームワークの崩壊と士気の低下
チーム崩壊のプロセスは、まるで病気の進行のように段階的に進んでいきます。
第1段階「初期症状」(月数~半年)
- 「また休みか」という小さな不満が蓄積
- チームメンバー同士の目線交換
- 「今日もいないのか」のため息
- 休憩時間の雑談に混じる愚痴
第2段階「中期症状」(半年~1年)
- 休憩室での本格的な愚痴が開始
- LINEグループ「○○さん以外」が作られる
- 「あの人の話はしないでおこう」の暗黙のルール
- 飲み会での批判がメイントピックに
第3段階「進行期」(1~2年)
- 「あの人の仕事はやりたくない」明確な拒否
- 情報共有からの意図的な除外
- 新人への「あの人は関わらない方がいい」アドバイス
- 他部署への悪口が拡散
第4段階「末期症状」(2年以上)
- 明確な派閥形成:「あの人の味方」 vs 「除外組」
- 会議での意図的な無視や情報閉鎖
- 新しいメンバーが定着しない状態
- 上司も「どうしたらいいか分からない」状態
最終段階「終末期」
- 「こんな職場にいたくない」優秀な人材が次々と離職
- 残ったのは仕事ができない人と、転職できない人だけ
- 企業文化の完全な崩壊、生産性の著しい低下
- 「あの部署だけは絶対偵めたくない」という社内レッテル
仕事をよく休む人が迷惑だと言われる原因5つ
具体的にどんな行動が「迷惑」「信用できない」と思われるのか、明確にしていきましょう。
連絡なしや当日の急な欠勤
最悪なのは無断欠勤です。しかし、無断欠勤までいかなくても、連絡方法やタイミングによっては同じように信用を失います。
最悪パターンランキング
- 無断欠勤 → 信用度:ゼロ
- 始業時間後の連絡 → 「もう仕事始まってるよ!」
- LINEで一言「休みます」のみ → 理由も謝罪もなし
- 理由を言わない → 「体調不良」だけで詳細不明
- 上司ではなく同僚にだけ連絡 → 伝言ゲーム状態
- 早朝すぎる時間の連絡 → 「6時30分に起こされた」
- 深夜の連絡 → 「明日休みます」の翌日0時30分メール
なぜこれほど腹が立つのか?
ビジネスの世界では「時間」がすべてです。急な欠勤連絡が引き起こす問題は:
- 対応時間の絶対的不足:代理探し、資料探し、スケジュール調整が物理的に不可能
- 連鎖的な混乱:一人の欠勤がチーム全体のスケジュールを崩壊
- 相手への配慮の欠如:「迷惑をかけてしまう」という意識が皮無
- 社会人としての基本マナー不足:報連相の基本すらできていない
特にフリーランスや個人事業主の場合、連絡なしのキャンセルは即座に「今後の取引停止」につながります。企業でも「信用できない人材」として記録され、今後のキャリアに大きな影響を与えます。
繁忙期や重要なタイミングでの休み
なぜかピンポイントで休む人がいます。月末の締め日には「わざとだろ」、繁忙期には「計画的すぎる」、重要な会議の日には「逃げた」、イベント準備日には「都合良すぎ」と周囲から思われ、信用度は最低レベルまで下がります。
休む理由が曖昧で一貫性がない
月曜日に「頭痛がひどくて…」、水曜日に「お腹の調子が…」、金曜日に「熱っぽくて…」、翌月曜に「めまいが…」。毎回違う症状は不自然で、一貫性のなさが不信感を生みます。
本当に病気なのか疑われ、仮病だと確信され、信頼関係が完全に崩壊し、本当に体調が悪い時も信じてもらえなくなります。
休まれることで迷惑に感じる心理的な背景
なぜこんなにもイライラしてしまうのか、心理的な側面を深掘りしてみましょう。
「自分ばかり損をしている」という感情
真面目な人ほど損をする構造があります。時間的損失として月20時間の追加残業でプライベート時間を失い、休日出勤月2回で家族との時間を犠牲にします。金銭的損失としてサービス残業分月5万円相当の無償労働、有給取得できずに年間10日分の権利を放棄します。健康的損失としてストレスによる不眠、過労による体調不良、精神的疲労の蓄積があります。
損をしている感覚が、やる気の低下、仕事の質の低下、職場への愛着の喪失、転職を考え始めるという負の連鎖を生み出します。
評価の不公平感と報われない努力
あなたは出勤率98%、残業月40時間、フォロー業務多数。一方、よく休む人は出勤率60%、残業ゼロ、自分の仕事のみ。それなのに評価は同じB、給料は同じ、ボーナスも同じ。
現実の声
「どんなに頑張っても、休みまくる同僚と評価が変わらない。もう頑張るのがバカらしくなりました」(20代・女性・販売)
職場の人間関係に与える悪影響
一人の欠勤が引き起こす職場の嵐として、フォローする人vsしない人の対立、「あの人の味方?」という派閥化、陰口・悪口の日常化、協力し合えない雰囲気、新人が定着しない、退職者の増加といった実際の人間関係の悪化が起きます。
よく休む人が発生する本当の原因を理解する
ここまでは「迷惑」「信用できない」という感情に寄り添ってきました。でも、少し視点を変えて、なぜその人はよく休むのかを考えてみることも大切です。
体調不良や持病を抱えている可能性
外見では分からない病気があります。慢性疲労症候群、線維筋痛症、過敏性腸症候群、偏頭痛、自己免疫疾患、内臓疾患、婦人科系疾患など、見た目は健康でも実は病気と闘っている人がいます。
「私は潰瘍性大腸炎を患っています。見た目は普通ですが、突然激痛に襲われて動けなくなることがあります。でも、説明しても理解されません」(30代・男性・営業)
メンタルヘルスの問題と向き合う現実
心の病は見えづらいものです。うつ病による無気力・不眠で朝起きられない、不安障害によるパニック・動悸で出社が困難、適応障害によるストレス反応で特定の状況で体調不良になるといった症状があります。
メンタル不調は5人に1人が生涯で経験し、治療には時間がかかり、周囲の理解が得られにくく、本人も苦しんでいるという現実があります。
家庭の事情や介護問題の存在
言いづらい家庭の事情として、親の介護(認知症、要介護)、子どもの不登校や病気、配偶者のDVやモラハラ、経済的困窮、離婚調停中、家族の精神疾患などがあります。
「母が認知症で、朝になると徘徊することがあります。でも、職場で『親の介護で』と言うと、『施設に入れれば?』と簡単に言われる。事情を知らない人に説明するのが辛いです」(40代・女性・事務)
信用出来ない人への建設的な対応方法5つ
理解はしても、現実的に困っている状況は変わりません。ここからは、建設的な対応方法を考えていきましょう。
感情的にならず冷静に対話する
「いつも休んでズルい!迷惑なんだけど!」ではなく、「最近体調が優れないようですが、何か職場でサポートできることはありますか?業務の調整など、一緒に考えられたらと思うのですが」という建設的な話し方をしましょう。
ポイントは、非難ではなく心配を示す、解決策を一緒に考える姿勢、相手の事情を聞く余地を残すことです。
上司や人事部への適切な相談
業務負担について具体的な残業時間を提示すれば人員補充や業務分担見直しが期待でき、頻繁な欠勤について客観的なデータで説明すれば本人への指導や配置転換、チームへの影響について売上や納期への影響を説明すれば体制の見直しが可能です。
相談時は感情論を避け、具体的な数字や事例を用意し、改善提案も一緒に伝え、記録を残しておくことが重要です。
業務の仕組みを改善する提案
改善提案として、業務マニュアルの整備、情報共有システムの導入、複数人でのバックアップ体制、フレックスタイム制の導入、リモートワークの活用、業務の優先順位の明確化などがあります。
よく休む人でも信用できるケースとその見極め方
すべての「よく休む人」が信用できないわけではありません。見極めるポイントを理解しましょう。
事前連絡と引き継ぎがしっかりしている
プロフェッショナルな休み方として、前日までに連絡がある、業務の引き継ぎ書を作成、緊急連絡先を共有、代替案を提示、締切や重要業務を事前に調整、復帰後にフォローアップといった特徴があります。
「持病で月2〜3回休む同僚がいますが、必ず前日に詳細な引き継ぎメモを残してくれます。おかげで業務に支障がないので、むしろ応援したい気持ちです」(30代・男性・エンジニア)
出勤時の仕事ぶりと成果で判断
休んでも成果を出す人は、短時間で高い成果を出す生産性、締切は必ず守る責任感、他者のフォローも積極的に行う協調性、代替が効かないスキルという専門性を持っています。
正当な理由がある場合の理解
受け入れるべき事情として、医師の診断書がある持病、家族の介護(介護認定あり)、不妊治療、障害や難病、労災認定された傷病、会社が認めた事情があります。
職場全体で取り組むべき改善策
個人の問題として片付けるのではなく、組織全体で改善していくことが重要です。
柔軟な働き方とフォロー体制の構築
導入すべき制度として、フレックスタイム制、時短勤務、リモートワーク、時間単位の有給取得といった柔軟な勤務制度と、チーム制の導入、ジョブローテーション、スキルの共有化、緊急時対応マニュアルというサポート体制があります。
業務の属人化を防ぐ仕組みづくり
全業務の手順書作成によるマニュアル化で引き継ぎ時間を短縮、クラウドでデータ管理による情報共有でどこからでもアクセス可能に、複数業務をこなせる人材育成による多能工化で欠員時の対応力向上を図ります。
相互理解を深めるコミュニケーション
効果的な取り組みとして、定期的な1on1面談、チームビルディング研修、メンタルヘルス研修、多様性理解のワークショップ、感謝を伝え合う文化づくりがあります。
よく休む人自身ができる信頼回復の方法
よく休む側の人も、信頼を取り戻すために努力することが大切です。
休む際のマナーと配慮の実践
最低限守るべきマナーとして、連絡はできるだけ早めに上司に直接し、理由を簡潔に説明し、復帰予定を伝えます。業務については緊急案件は必ず引き継ぎ、資料の場所を共有し、代理対応者を指名し、お客様への影響を最小限にします。
出勤時の積極的な貢献
休んだ分を取り返す姿勢として、難しい案件を引き受ける率先した仕事、同僚の仕事を手伝う他者のサポート、資格取得や勉強会参加によるスキルアップ、業務効率化の改善提案があります。
同僚への感謝と協力の姿勢
信頼回復のための行動として、フォローしてくれた人に直接お礼を言い、差し入れやお土産(やりすぎ注意)、他の人が休む時は積極的にフォロー、仕事で恩返し、チームの雰囲気づくりに貢献、前向きな姿勢を保つことが大切です。
誰もが働きやすい職場環境を目指して
最後に、「よく休む人 vs 休まない人」という対立構造を超えて、全員が働きやすい職場を作る方法を考えてみましょう。
多様性を認め合う職場文化の重要性
様々な事情を抱える人々がいます。子育て中の親、介護をしている人、持病がある人、メンタル不調と闘う人、障害を持つ人。それぞれの強みもあります。短時間で高い成果を出す人、長時間安定して働ける人、クリエイティブな発想ができる人、ルーティンワークが得意な人。全員が同じでなくていいのです。
多様性がもたらすメリットとして、イノベーションの創出、離職率の低下、企業イメージの向上、生産性の向上(長期的に)、優秀な人材の確保があります。
お互いを支え合うチームワークの構築
従来の「全員が同じように働くべき」「休む人は迷惑」「個人の責任」「我慢が美徳」という考え方から、「それぞれの事情に配慮」「休むことも権利」「チームで支え合う」「健康第一」という新しい考え方への転換が必要です。
理想的なチームの例として、「うちのチームは『お互い様』の精神が根付いています。誰かが休んでも『大丈夫、カバーするよ』と自然に言える。結果的に全員のパフォーマンスが上がりました」(30代・女性・マネージャー)があります。
より良い職場環境への前向きな変化
これからの職場に必要なこととして、意識改革では「迷惑」から「お互い様」へ、「我慢」から「助け合い」へ、「競争」から「共生」へ。制度改革では柔軟な働き方の導入、評価制度の見直し、福利厚生の充実。文化改革では心理的安全性の確保、多様性の尊重、感謝の文化づくりがあります。
変化は少しずつでいいのです。今すぐすべてを変えることはできませんが、一人一人の意識が変われば、職場は必ず良い方向に変わっていきます。
あなたができることは、まず相手の事情を想像してみる、「ありがとう」を言葉にする、自分も無理をしすぎない、建設的な提案をする、お互い様の精神を持つことです。
「よく休む人は信用できない」その気持ちは、よく分かります。本当に大変な思いをされているでしょう。でも、その人にも事情があるかもしれません。そして、あなたもいつか、休まざるを得ない状況になるかもしれません。
大切なのは、お互いの事情を理解し合い、支え合える職場を作ること。完璧な人間なんていません。みんな何かしらの事情を抱えながら働いています。
だからこそ、お互いを認め合い、助け合える職場環境を目指していきましょう。きっと、そんな職場で働けたら、「よく休む人」も減るし、「信用できない」という気持ちも和らぐはずです。
あなたの職場が、もっと働きやすい場所になることを願っています。





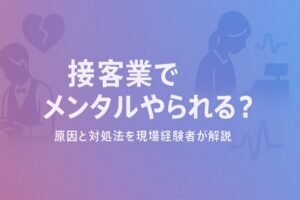




コメント